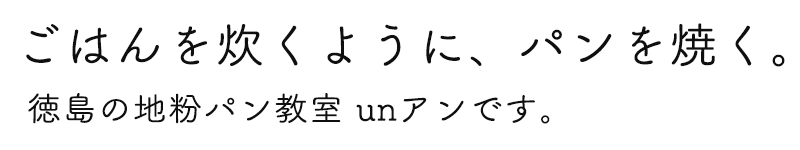茶摘みと烏龍茶づくり
黄金週間真っ只中の5月2日。神山町の江田にある茶畑で茶を摘み烏龍茶をつくる、というワークショップに参加した。
神戸から遊びに来ていた友人家族と一緒に参加できたこともうれしい。ご配慮いただき感謝◎
「一芯二葉」の茶葉を摘んでいく。

二葉の間にすくっと伸びる若い芽。
3時間くらい、ひたすら茶葉を摘む。
摘んでも摘んでもなくならない。
植田さん曰く、剪定をせずのびのびと育てているそう。茶木の根元にたくさん敷かれている「茅」の話もとても興味深くて。昔は良い土づくりのためにあちらこちらで使われていた「茅」は、運ぶだけでも重労働。お年寄り世帯だけではなかなか続けられない。茅葺き屋根がある地域は、どこも土がとても良い状態だそうで。自然の産物を地域で循環させていることがよくわかる光景、ということもとても興味深かった。そういう視点で風景を眺めると、楽しいだろうなぁ。
摘んだ茶葉は30分程度お日様に当て、水分を蒸発させる。茎を持った時にクニャッとしなるくらいになるとちょうどいいんだって。
茶葉に細かい傷をつけながら発酵を促すべく、揺すり続けること…1時間以上。烏龍茶は「半発酵茶」と呼ばれる種類で、発酵具合の幅がとても広いのだそう。今回は1日で仕上げるワークショップだったので、浅い発酵で仕上げることに。
水分を飛ばすように火にかけ、熱くなった茶葉をぎゅっと丸めて圧をかけていく。
何回か繰り返すと、茶葉がクネクネしてくる。
これを火にかけ、水分を飛ばしていく。
時間が経てば経つほど、香ばしい香りが広がってきた。
最後の仕上げは天日で。
今回、教えていただいた堀口一子さん。試飲させていただいた烏龍茶も白茶と呼ばれる炒らないお茶も、とてもおいしくいただきました。何より、こうして一杯ずつ丁寧にお茶を淹れる時間があるだけで、スーッと気持ちが鎮まるなぁと感じます。

左側が茶畑
想像以上においしい…。
もう一度自力でできるかと言われたら…多分できない。ずっと揺すり続けたり、炒り続けたり、とにかく丸一日かかりっきりで仕上げたお茶。こんな贅沢な時間の過ごし方、家ではなかなかできないよな〜と。
手間暇かけた贅沢な時間の結晶。残りの烏龍茶は一緒にお茶を味わってくれそうな叔母に届けようかしら。
樋口 明日香